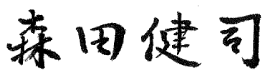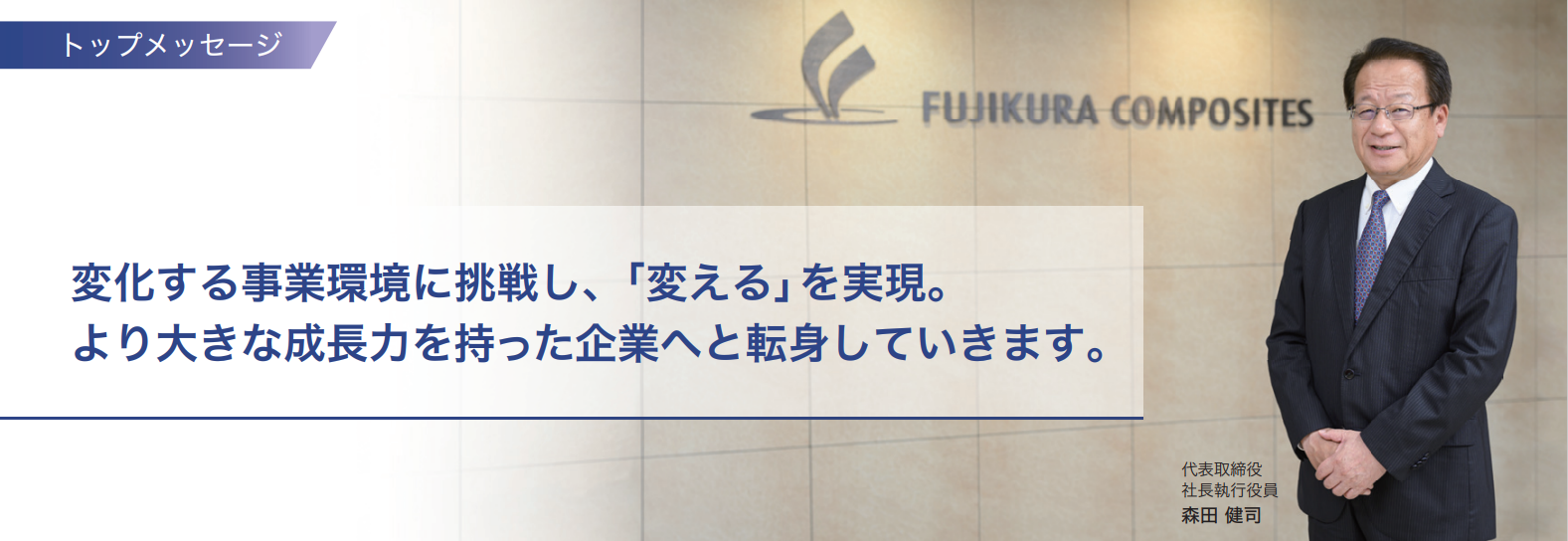
変化する事業環境に挑戦し、「変える」を実現。
より大きな成長力を持った企業へと転身していきます。
企業ビジョンと「5 つのささえる」
卓越した複合化技術で、
世界を多様な側面からささえる企業として
藤倉コンポジットは、卓越した複合化技術(コンポジット技術)で豊かなくらしをささえるグローバルカンパニーを目指しています。例えば、創業から123年の間に蓄積してきた技術力や経験と、時代や社会から要求される技術とのコンポジット。あるいは匠の技術を持つベテラン技術者と、新しい発想を持った若手技術者とのコンポジット―材料だけでなく、あらゆるものをコンポジットすることで新しい可能性を生み出して未来のカタチを実現し、社会をささえることを私たちの使命としています。 当社では、世の中に提供している製品や事業領域を「5つのささえる」で表現しています(「くらしをささえる」、「ものづくりをささえる」、「エネルギーをささえる」、「いのちをささえる」、「レジャーをささえる」)。まず、「くらしをささえる」では、電気・ガス・水道を制御するライフライン機器、電気・ガス給湯器、キッチン・お風呂・トイレなどの住宅設備内にある水栓機器、スピーカー・消音部品などの音響機器など、普段の快適な生活をささえる基盤にある部品を安定して供給しています。
また、産業用としては半導体製造装置、液晶製造装置など、精密な作動制御を特徴としたエアーレギュレーターや除振設備の需要が高まっており、それに対応すべく供給を行っています。
次に「エネルギーをささえる」です。当社は、長年送電設備の中継機器用シール材を供給しています。特に高圧電線の供給や、電線の地中化などには中継部分の品質安定性が求められます。また、風力発電設備のブレード部分を保護するシートを供給しています。ブレードは嵐や雹、バードストライクなどで破損しやすく、それを保護することでブレードの長寿命化に貢献しています。その他、災害に伴う停電が発生しても、スマートフォンなどの通信電力を確実に確保できる非常用マグネシウム空気電池(商品名:WattSatt)も供給しています。
そして「いのちをささえる」では、主に医療関係の部品を製造しています。1985年から福島県の工場にクリーンルームを設け人工透析器用パッキンを供給してきましたが、新たに2020年に同工場内にクリーンルームを大規模に増設、シングルユース部素材を主に供給しています。この部品は今までは海外からの輸入に100%頼っており、国内で生産・供給するメーカーがありませんでした。それを唯一当社が実現しました。通常はバイオ医薬用を、有事の際は国産ワクチン用も製造します。なお、ワクチン国産化を推し進める一環としてシングルユース関連製品の開発および製造推進のため、シングルユース関連の部素材メーカーが集まった共同体である「J-STAC※」が結成されており、当社も積極参画しています。この他にもいのちの分野で国内唯一のメーカーとして「救命いかだ」の製造を長年行っており、世界各国の船舶に供給しています。一昨年の知床の海難事故をきっかけに、中型船にも救命装備の追加を義務化すべきということで国土交通省から依頼を受け、開発を行いました。政府による救命具導入の補助金が適用になったこともあり2024年度から受注を開始しています。
最後の「レジャーをささえる」はゴルフシャフト、登山靴の2つの事業を行っています。ゴルフではカーボンシャフトを製造しており、現在「Fujikura Shaft」として世界一のブランドを確立しています。特にアメリカで開発した「VENTUS」は米国PGAをはじめ、欧米および日本のプロツアーで使用率トップを維持しています。日本人の体格に合わせて開発した「SPEEDER」シリーズも非常に高い評価をいただいています。2023年度は逆に「VENTUS」を日本で、「SPEEDER」をアメリカで発売しましたが、ターゲットの異なる商品ということもあって、相乗効果が生まれ、2ブランドとも販売が伸びました。当社の市場シェアは、プロからアマチュアの皆様を含め、世界50%超と推定しています。株主の皆様からも非常に好評だったこともあり、当社株を500株以上保有されている方にシャフト1本進呈の株主優待を2023年度から始めました。こちらも大変評判が良いようです。もう一つの事業は、登山靴の老舗ブランド「キャラバン」の展開です。海外で生産しているため2023年度は円安の影響でコスト増になったこと、また使用環境として雪が少なかったということもあり厳しい一年でしたが、非常に高いシェアを持つブランドですので早期に挽回していきます。
当社の製品はどれも長きにわたって社会の中でしっかりと根付いていると自負しています。今後も社会や市場の変化に対応する製品を次々と供給し、社会をささえていきます。
2023年度の振り返りと中期経営計画の進捗
価格転嫁の困難が続く中、収益を確保。
「変わる」から「変える」へ、組織と人材の変革を実現
2022年のウクライナ侵攻に続いて、2023年は中東地域でも戦闘が発生し、地政学的なリスクが非常に高まり、世界的な物流、サプライチェーンの混乱が続いた年でした。一方、国内はアフターコロナに切り替わり、外食やレジャー、インバウンド需要が戻りつつあります。しかしながら日本には少子高齢化による人手不足や低賃金、低金利といった構造的な課題が山積しています。さらに、自動車産業で検査不正などの問題が多発しました。当社においては、日ごろから生産性向上による原価低減活動を推進継続しておりますが、昨今の原材料費、エネルギー費、輸送費などの急激なコスト増の波がそれ以上に大きく、やむなく製品価格転嫁を実施しております。2024年度も引き続き粘り強く交渉を行ってまいります。
各セグメントの収益状況ですが、産業用資材セグメントの工業用品部門は流通在庫、メーカー在庫がともに過多となり減収減益となりました。一方の海外は、中国、ベトナム、アメリカの受注が徐々に回復し、価格転嫁も海外の方が順調だったため、固定費削減分も含めると増益となりました。制御機器部門の半導体、液晶の市場では減産が続き、一部、医療市場にも流通在庫の停滞があり、若干の減収減益でした。
引布加工品セグメントは、引布部門では主に建築材料用の防水シートが堅調に推移し、増収増益となりました。加工品部門は海外の救命いかだ、防衛省向けが堅調に推移しましたが、国内の舶用品、救命いかだは低調でした。また、同じセグメントの印刷材料部門でオフセット印刷用ブランケットを供給していましたが、デジタル化の進展により印刷市場が縮小、採算性の課題があり、期中に撤退を決定しました。これらの結果、引布加工品セグメント全体は減収、若干の営業赤字という結果でした。
スポーツ用品セグメントでは、コロナ禍でゴルフ人口が増加し、2022年度は各メーカーが市場への投入量を増やしたため、2023年度は流通在庫の過多が予測されていました。期初にも減収減益を予測していましたが、主力モデルのアフターマーケット市場が好調となり、減収幅は想定より小さく留まったことで、引き続き、高い利益率を維持できました。アウトドア用品部門は暖冬の影響により冬物商品の出足が遅れたものの、第4四半期に若干盛り返し、増益となりました。
これらの結果、当社グループの連結業績は前年度と比べて売上高、営業利益ともに減少となりました。
現在取り組む「第6次中期経営計画 TRANSFORM」は、コロナ禍による事業環境の変動を見越し、2020年度から2024年度の5ヵ年の計画といたしました。前半3ヵ年を回復期、後半の2022年度から3ヵ年を成長期と定義しています。営業利益率平均10%以上を主要指標とし、「変化にチャレンジし、『変わる』から『変える』へ」を掲げ、事業改革に取り組んできました。例えば、原材料価格の高騰により収益率が著しく低下したビジネスをどうすべきか、個々の製品の真の原価を算出して見直しをしました。営業のやり方も世の中の変化に合わせて変えていこうという議論をし、事業ごとに投下した資本に対して利益が得られているか、資本効率の観点から見直しを行ってきました。それらの取り組み結果の一つとして、印刷事業からの撤退の決断に至りました。また、生産体制についても、国内外のアロケーションを見直し、変えていくべきだと捉えています。
このような事業や組織の変革とともに、肝心な事は従業員の意識改革です。上下関係や部門の隔たりを超えて、意見を言い合える文化に変えていきたいと「さん付け運動」を定着させてきました。また、コロナ禍ではオンライン環境を利用しながら、年度の初め、年初などに私の考えを全従業員に伝える機会を設けています。生産現場については設備投資レビュー、品質レビューおよび安全パトロール等を兼ねて全工場を回っています。さらに、人的資本に対する投資の拡大も検討しています。アンケートによって従業員の声を収集し、それに基づいて複線型の総合職の選択肢を設け、個々の従業員のキャリアイメージに基づいた再教育、育成などを実施していきます。 そして、国内の従業員だけではなく、海外の当社グループ従業員も非常に大切です。海外渡航の制限も解除されましたので、海外当社グループ拠点を中心に全世界を回る計画をしています。

サテナビリティ経営
マテリアリティに沿ったロードマップを描き、
サステナビリティ経営による企業価値向上へ
昨今の急速な外部環境の変化を柔軟に捉えつつ、当社の社会的価値および存在意義を向上させるために、サステナビリティを経営の中に取り入れることが非常に重要であると考えています。
具体的には2024年4月から社長直轄の組織として新たにスタートしたサステナビリティ統括室主導の下、役員を対象としたサステナビリティ勉強会を実施しました。社内外の役員の議論内容を反映しながら、人権尊重、環境保護、社会貢献、リスクマネジメントなどの基本方針を見直し、マテリアリティをはじめ各種重要事項の取り組みを強化していきます。また、活動の優先順位をつけてロードマップを描いていくことが肝要だと思っています。
核になるマテリアリティについては、社内外役員の中で議論に議論を重ね策定し、発表しました。当社の事業と社会課題との関わりを明確にし、それらを体系的に捉えていくため、このマテリアリティの特定が非常に重要と感じています。それらに対する具体的取り組みを事業部長中心に検討し、個々の項目に対してしっかりとKPIを定めて実行、社内外役員が都度進捗状況を確認し監督を行っていきます。
特に地球温暖化の加速に対する対応は全世界の喫緊の課題であるとともに、当然ながら当社においても早急な対応が必要であると認識しています。
2021年に日本政府が目標として掲げた「2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指す。2050年までにカーボンニュートラルを目指す」を当社としても重く受け止め、その目標を踏襲して2023年度に全社目標として掲げました。当然ながら非常にハードルの高い目標であることは認識していますが、後世へ負の遺産を絶対に渡さないという使命感を持って誠心誠意取り組んでまいります。先述したKPIにもこの地球温暖化対応を盛り込んでいきます。
現在、生産活動全体での取り組みの重要性が高まっています。当社グループ独自の活動に留まらず、サプライチェーン全体での活動をしっかり把握し、コントロールすることが求められています。当社の取り組みを広くステークホルダーの皆様にお伝えできるよう広報活動も充実させてまいります。また、公共性のあるアンケート・調査にも積極的にお答えし、課題・問題点を明確にしてまいります。
ガバナンスに関しては、当社は2023年6月の株主総会の決議をもって、監査等委員会設置会社に機構の変更を行いました。さらに、2024年6月の総会で社外取締役監査等委員1名の増員を承認いただきました。社外取締役監査等委員3名と取締役常勤監査等委員1名で監査等委員会を構成し、経営の監督と執行の機能分離と取締役会の実効性向上に取り組んでいきます。さらに、経営戦略強化を図るために経営戦略委員会(仮称)を新たに設置しました。ここでの議題は主に2つで、一つは中長期的な観点からの経営重要課題の抽出、もう一つは経営会議の実効性評価です。例えば、当社は現在、既存事業の稼ぐ力の強化とともに新成長戦略に取り組んでいますが、新規事業を自前のリソースで立ち上げるのには非常に大きな時間を要します。できるだけ早く新しい事業の形を作っていくには、外部リソースの活用が必要です。当社は、2023年9月にシンガポールのFuYu社との業務提携を発表しました。今後の注力市場に定めたEV分野における複合化製品を両社で開発していきます。また、相互の技術シナジーとマーケットを生かし、半導体・医療市場向けのアプローチも視野に入れています。このような成長事業への展開も経営戦略委員会の中でさまざまな評価、検討を継続していく予定です。さらにサステナビリティ関連投資についても同委員会で検討し、そこで議論した結果を取締役会にて最終審議をします。
また、将来に向けた基礎研究の充実と開発体制の強化を図るべく、2024年4月より社長直轄組織として先進技術戦略室を設置しました。従来からある技術開発部の枠組みをさらに広げ、技術企画の機能推進、および外部リソースの有効活用による新たなイノベーション創出を図ります。まず初めに行った事例として、AIやMI(Materials Informatics)を応用した基礎研究の充実による、開発期間の大幅短縮に向けた取り組みや、社内エントリー制度を活用した開発体制の創設などがあります。
2023年に日本企業の低PBRについて株式市場から指摘がありました。当社のPBRも直近でも1倍の水準を超えておらず、早急に対処しているところであります。具体的には、先に述べた稼ぐ力の強化、新成長戦略、新株主還元方針、投資家とのコミュニケーションの4つの観点から各種施策を実行していきます。従来通りの決算説明会などIRイベントや活動の他に、国内外の投資家との個別面談などを積極的に開催する計画です。
ステークホルダーの皆様へ
強みを生かし、持続可能な社会の実現と
企業価値の向上を目指す
今回のマテリアリティ策定においても議論を重ねてきましたが、藤倉コンポジットのサステナビリティは、当社の強みである複合化技術を用いて、あらゆる市場に価値を提供し、社会に貢献していくことだと考えています。目まぐるしく変化する時代の中でも、特にエネルギーや医療の分野は常に社会課題として挙げられており、まさに当社がそれらに対する貢献を大きくしていくことでお客様のお役に立つことができるとともに、株主の皆様とのお約束も果たしていけると考えます。また、従業員とのコミュニケーションを通じて、多様な人材が活躍できる職場づくりを進めていきます。これからもステークホルダーの皆様とともに変化にチャレンジし、豊かなくらしをささえていくことで、持続可能な社会の実現と企業価値向上を推し進め、地球環境全体の改善へ貢献していきます。

藤倉コンポジット株式会社
代表取締役社長執行役員